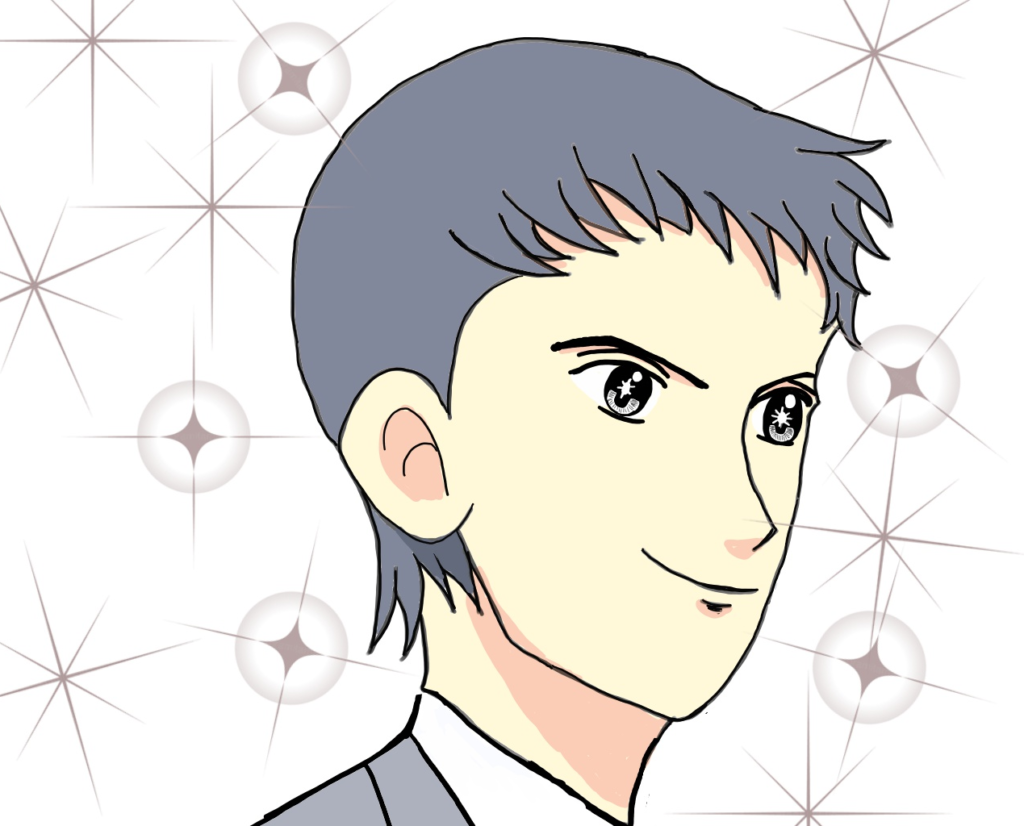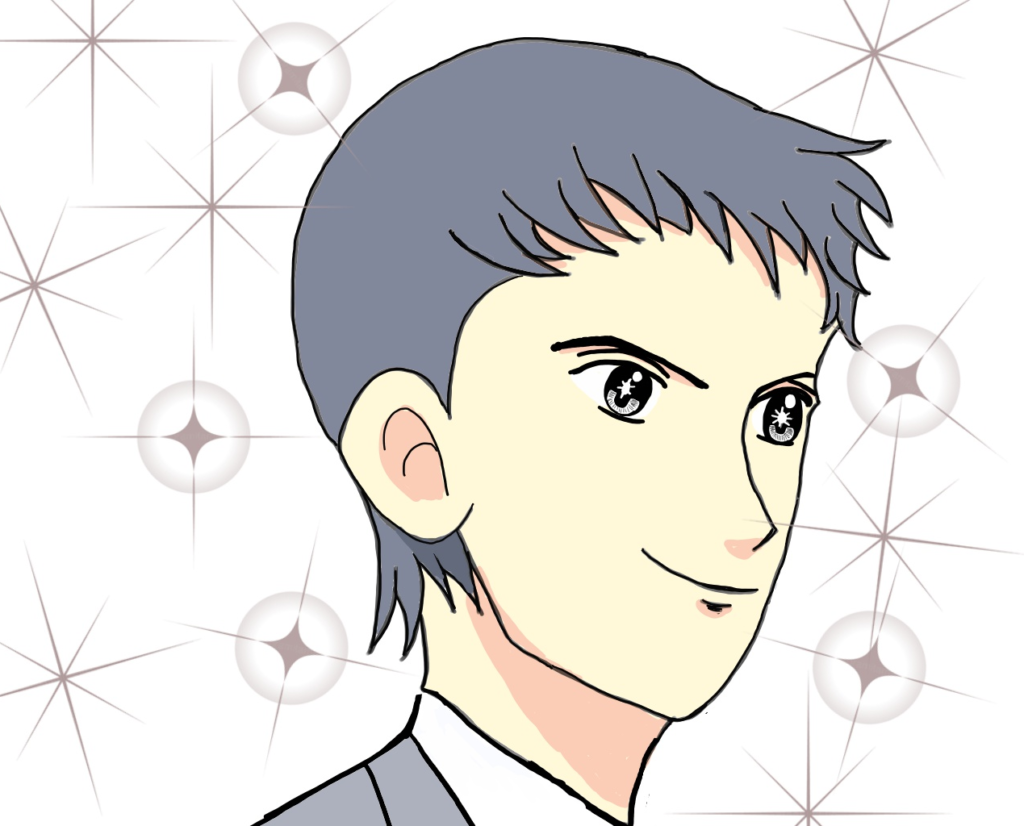

「生成AIと知財業界」です
当社でも特許事務所のDXにおいて、生成AIは救世主になりそうといろいろ開発中です。
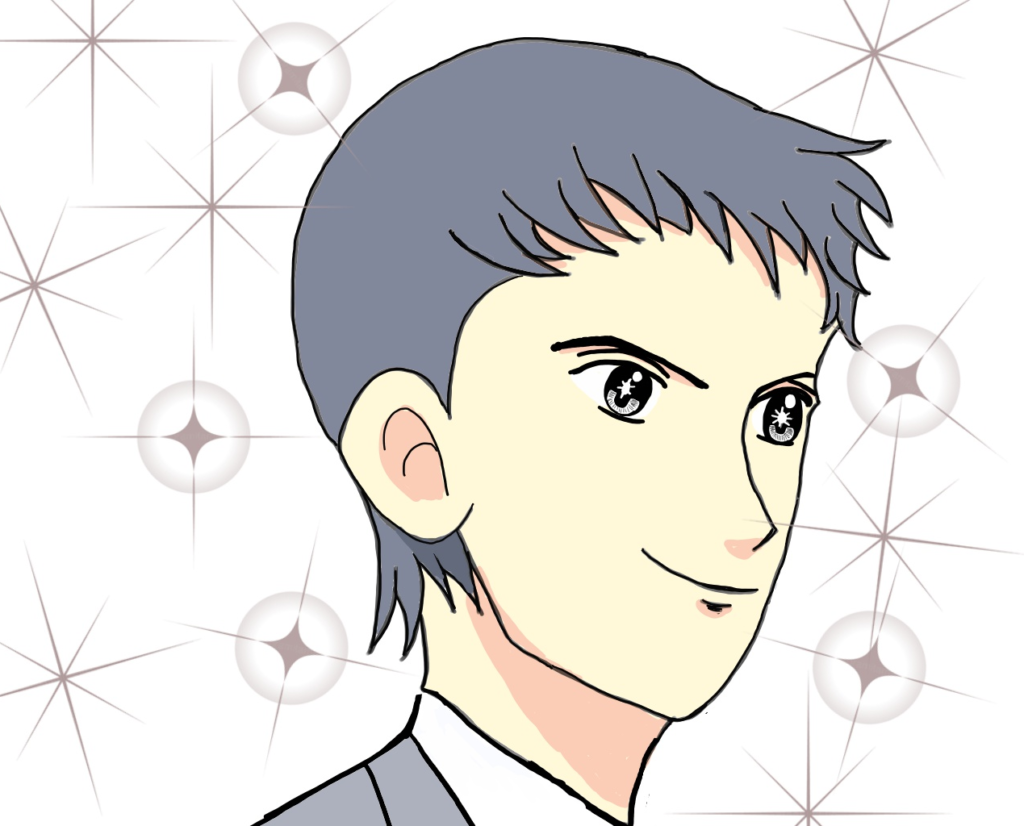
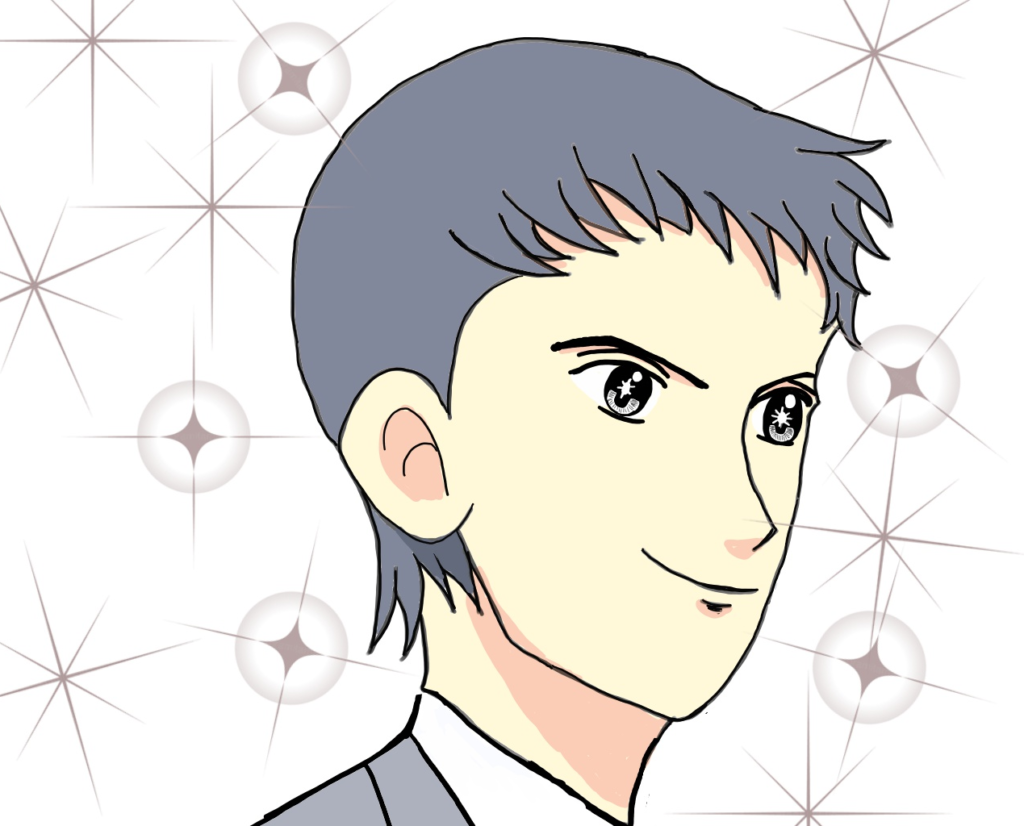
本記事の内容
(1)AIと知財
AIと知財――この組み合わせが本格的に注目され始めたのは、特許調査の分野でした。2017年頃から「人が読むには多すぎる特許情報を、AIで要約・俯瞰・戦略的解釈する」という方向で、ディープラーニングの活用が注目されました。次に、画像認識AIが登場し「意匠・商標の類比判断」にも応用され始め、2019年には、「AI vs 弁理士 商標調査対決」が開催され話題を呼び、実務へのAI導入の可能性が示されました。
当時は「AIが弁理士を代替する」といった話もありましたが、明細書作成や翻訳などの高度な知的作業にはまだ遠く及ばないというのが共通認識でした。
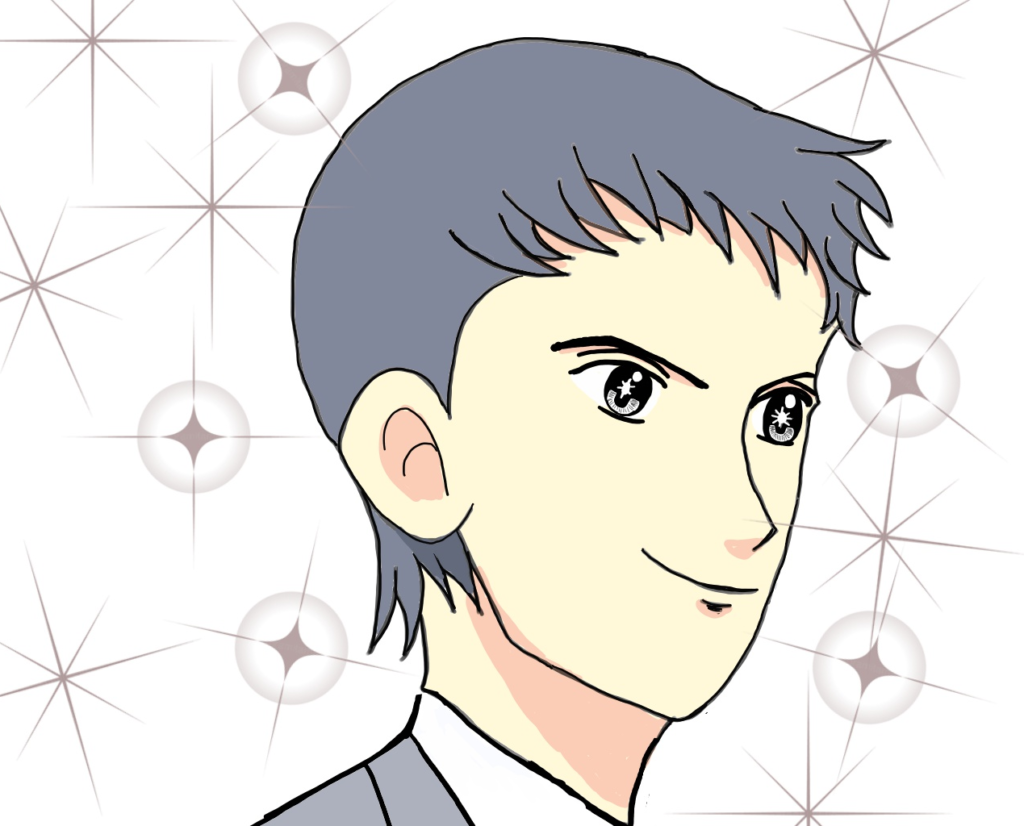
(2)ChatGPTの登場が変えた景色
2022年以降、OpenAIのChatGPTをはじめとした**生成AI(Generative AI)**の登場により、知財業界も急速に変化し始めました。
従来、テンプレートベースやルールベースでしか対応できなかった明細書作成が、プロンプト次第でかなりの精度で自動生成できるようになりました。ある程度の技術情報を入力するだけで、請求項から実施例まで整った文面を出力することが可能です。
また、翻訳の分野では人間の精度を凌ぐケースも珍しくありません。
特に明細書の翻訳文作成においては、生成AIの出力は非常に安定しており、某ベテラン弁理士の先生からは「もう人間翻訳には戻れない。人間の方がミスが多い」といった声も聞かれます。
これまで「AIって言っても、せいぜい検索の補助でしょ?」というレベルだったのが、
生成AIが出てきたことで、「え、これ明細書書けちゃうじゃん」と実感する場面が増えてきましたね。
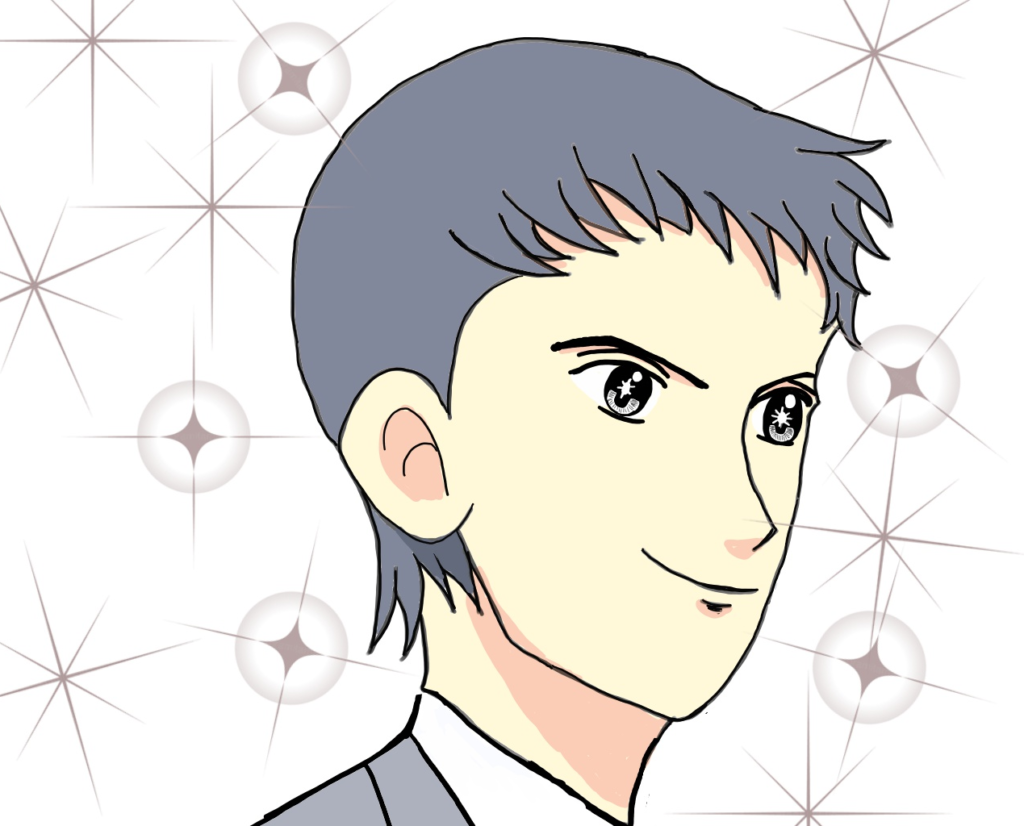
(3)調査・IPランドスケープはまだ人間の領域?
一方、特許調査やIPランドスケープの分野では、生成AIの活用は進んでいるものの、まだまだ「人間の直感」に依存する場面が多いと感じます。
特許分類をまたぐような異分野融合技術や、文脈を踏まえた用途探索、新しい事業の方向性を示唆する分析などでは、「これは何か面白い」と気づくには人間の目が必要です。
とはいえ、生成AIによる事前の資料生成や俯瞰マップの作成など、アシスト役としての存在感は日々高まっており、AIが「気づきのきっかけ」を与えてくれるレベルには到達していると感じます。
ここにきて生成AIが登場したことで、むしろ「明細書の自動生成」のほうが一気にレベルアップした感じがあります。
「え、こっちのほうが先に実用レベルに来ちゃうの?」みたいな逆転現象ですね。
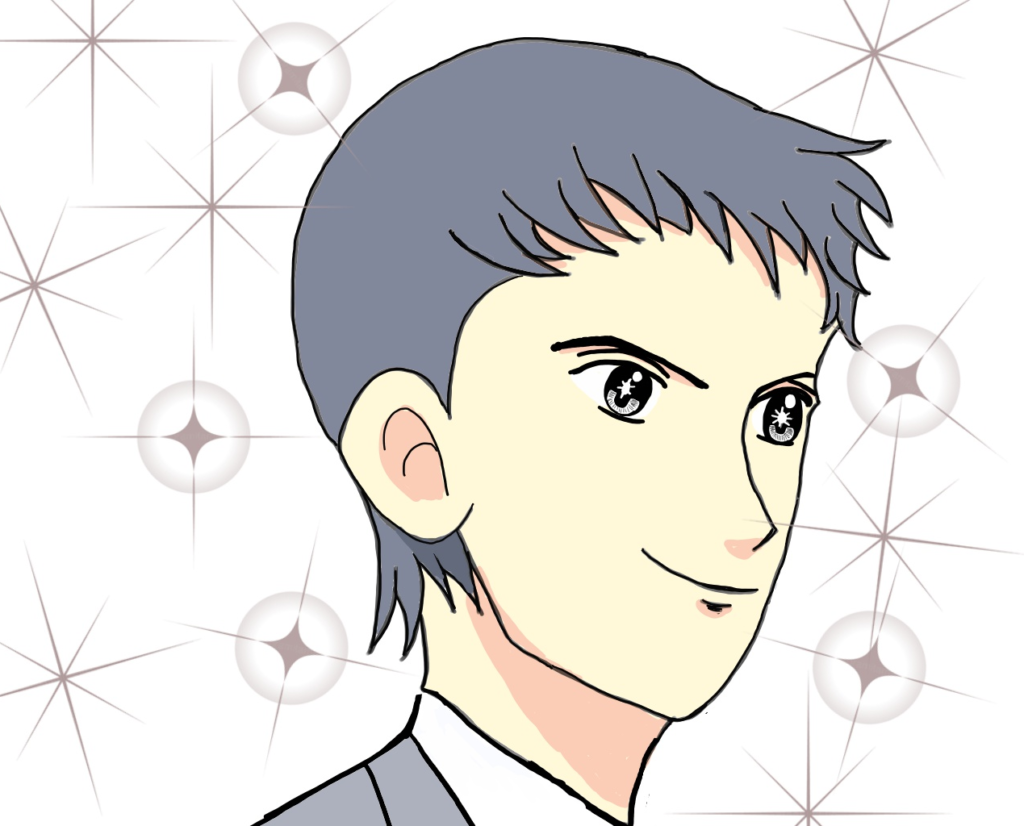
(4)まとめ:AIを操る専門家へ
今後は、生成AIの進化によって、知財業務の多くは効率化され、「人間がやらなければならない作業」は確実に減ってくと予想されます。
そのため、知財業界では求められるスキルは大きく変わっていくと考えます。
例えば、明細書作成や図面作成は、AIが担うようになり、人間の役割は「プロンプト(指示)の出し方」に集約されていくのではないかと考えられます。これは、3DCADの登場で意匠図面作成において**「デッサンスキル」が不要になった**変化とよく似ています。
重要なのは、何を、どのように、どこまで伝えればAIが適切に出力してくれるかを知ること。
-
技術的背景を的確にAIに伝えるスキル
-
意図する権利範囲を構造的に表現する力
-
AIの出力結果を見て評価し、微調整を加える判断力
AIをどう使いこなすか。どんな問いを立て、どんな形で権利化に導くか。
という「知的レベルの高いクリエイティブな仕事」が中心になるのです。
ChatGPTさんには、テーマの項目と結論を指示してブログ書いてもらいました。
どこまで本当かわからないですが、ちゃんと記事になっていると思います。すごいですね。本当にAIの使い方は未知数で、今後どうなっていくのか非常に楽しみです。